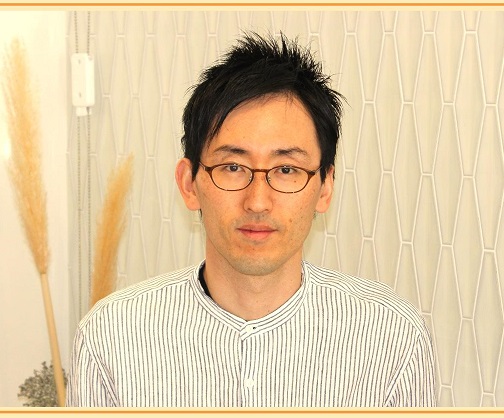理念・ポリシー |
~こころとからだのつながり~ |
| ||||
~病気がおしえてくれること~ |
| ||
そうなると、むしろ非科学的なのは科学的な治療の枠に収まらない私達<人間>という存在なのではないか、と考えるのが適切かもしれません。 もちろん私達の体は物質でできており、感情や思考は脳の発達と無関係ではありませんが、実際には器質的な原因がない精神疾患があったり、発達障害など他者との比較による診断基準により本人にとっては正常でも社会的に病気や障がいだと扱われてしまう事もあります。 人間をただの物質として診断・治療するのには、人間という存在をを理解すればするほど無理があります。高度な精神性を持っているからこそ、もっと大きな世界観(福祉・社会・倫理・宗教観など)を理解していくこと、より一人一人に誠実かつ正直に対応して治療やリハビリテーションをしていく必要に医療や代替療法は迫られている気がします。 以下は実際にWHO(世界保健機関)が定める健康に対する定義の一説になりますが、 『健康とは肉体的、精神的、社会的、宗教的にも健やかでダイナミック(活力がある)な状態』とされていて、なおかつ『肉体に病気や障がいがない状態の事をいうのではなく』と添えられています。 このような実情を踏まえると、私達が病気になる原因は身体的・物理的な状態だけではなく、その人や社会を取り巻くあらゆる状況(家族関係・学校・職場・また性の問題・個人的な生き方・さらには社会的な公衆衛生や価値観)までも何らかの要因があるかもしれません。 そういう意味では、「ストレス社会」という言い方をしますが、一人一人の疾患の中に世界を見出すこともできる気がしています。つまり「心をないがしろにしては人も社会も健康になれない」のです。 |
~カウンセリング・セラピーの目的~ |
|
・ある人はムシャクシャしていたので、空き缶を蹴っ飛ばしました。
・次の人はその空き缶を見て、帰りにコーラを買っていきました。
・最後の人は転がった空き缶を拾って、ゴミ箱に入れました。
このように、コーラの空き缶に対する反応は人それぞれ異なっています。つまりコーラの空き缶に対して各々のこころの反応が行動の違いに現れたわけです。そうなると、外側の世界にあるコーラの空き缶に良い悪いはなく、内側の心の状態によって反応が変わることになります。
人間は全ての生物の中で唯一「私は人間である」という自己認識(エゴ…自我)を持つ存在と言われます。しかし自分自身は鏡を使わないと見えないので、<周囲に投影する>という方法で鏡を作り出します。
その投影先は『他人…親・家族・友達』だったり、『環境…学校・職場・家庭』だったり。そして究極は『身体』にも投影することがあるようです。簡単に言うと外側の何かに『責任転嫁』します。
こういう出来事はある意味で人間らしい話ではありますが、これが苦痛の始まりだったりするわけです。なぜなら、外側の世界は変えることができないからです(ただの鏡なので割っても世界が変わるわけない)。
前項目の「人はどうして病気になるのか?」で、その人を取り巻く状況も含めたところに要因がある…とお伝えしました。なのに、世界は変えられないとなったら私達はどうしたらいいのでしょうか?
その答えは、振り出しに戻りますが(笑)…世界の成り立ちに気付くと自ずと答えが出てきます。つまり『自分が変わる』ことで必ず『世界が変わる』ことになります。
その理由は「世界は一枚の鏡」だからです。
カウンセリングもセラピーも、この「鏡の法則」を利用して行われ「本当の自分」に気づいてもらうために行うという目的があります。つまり、コーラの空き缶を蹴った<自分>の心境に気づくこと、コーラを飲みたくなっている<自分>の心境に気づくこと、コーラの空き缶をゴミ箱に捨てた<自分>の心境に気づくことで、自分を知ることができるわけです。
この気づきを得ることは難しくても価値があり、ここから自己変化(治癒…セラピー)が始まるのです。